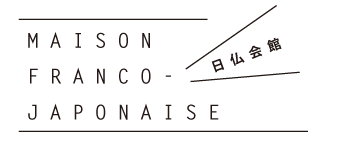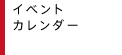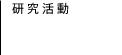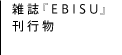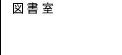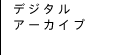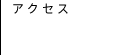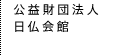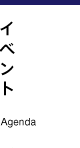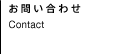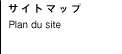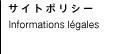2025年4月のイベント
- ニール号、万国博覧会史の仏日共有海事遺産
- 日仏翻訳マスタークラス
- 1995-2025:東京湾ウォーターフロントの都市革命
- Entre philologie et linguistique : éléments de méthodologie pour aborder les textes missionnaires en japonais romanisé
| 日時: | 2025年04月11日(金) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
| 講演者: | 木村淳(東海大学) |
|
フランスは、国際社会でいち早く、水中考古学を推進する国立の研究機関を立ち上げた歴史がある。日本においても海底遺跡の研究の歴史は古く、近年では、近代の沈没船遺跡の調査保護が進んでいる。静岡県伊豆半島南伊豆町沖合の海底には、メッサージェリ・マリティム社所属であったニール号の残骸が沈没船遺跡として残されている。 木村淳は東海大学人文学准教授。フリンダース大学院PhD修了後、マードック大学アジア研究所、シカゴ・フィールド自然史博物館研究員を経て現職。専門は海事考古学・水中考古学。アジアの沈没船遺跡研究を専門としている。主な著書に『Archaeology of East Asian Shipbuilding』、『海洋考古学入門:方法と実践』、『図説 世界の水中遺跡』。KUルーベン大学客員教授、文化庁水中遺跡調査検討委員会有識者委員、ICOMOS水中文化遺産国際委員会委員。先史時代のウンブキ水中鍾乳洞遺跡、ベトナムでの海上シルクルート交易沈没船調査、太平洋マニラガレオン船調査を行っている。2017年から伊豆半島沖のフランス郵船ニール号の調査を実施している。 【講師】木村淳(東海大学)
|
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年04月12日(土) 15:00~18:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
| 講演者: | カトリーヌ・アンスロー(会議通訳、翻訳者) |
定員に達したためお申込みを締め切りました2015年小西財団日仏翻訳文学賞受賞者のカトリーヌ・アンスロー氏の指導による、日本語からフランス語への実践的な翻訳ワークショップ(全6回のうちの第4回目)
カトリーヌ・アンスロー
お申込み
お申込み方法 【主催】日仏会館・フランス国立日本研究所 |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年04月21日(月) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
| 講演者: | レミ・スコシマロ(トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学) |
この講演会へのお申し込みは、4/14(月)にオープン予定の新しいWebサイト上で受け付けます。過去30年間、日本の海面埋立地は継続的な変容を遂げてきた。都市の外延的な拡張は港湾区域の制約により鈍化したものの、これらの空間では絶えず再開発が進められている。もともと港湾および物流機能を主とするエリアとして形成されたが、近年では都市機能が進出し、新たな都市的ダイナミクスが生まれつつある。 こうした埋立地の発展は、産業的遺産、都心への近接性、そして独特の土地利用の自由度を背景に、革新的な都市開発を促進してきた。これらの新しい市街地は、従来のジェントリフィケーションのプロセスから部分的に逸脱し、日本の都市計画における実験的なフィールドとなっている。 この変容は都市空間の不均質な勾配を生み出す一方で、ウォーターフロントの一般開放によって、日本の都市とその沿岸地域との関係性が大きく再編された。これにより、都市空間の一部としての埋立地の統合が進み、同時にグローバル化が進行する都市景観が形成されている。本研究では、この空間変容がもたらす社会経済的・人口学的な影響、とりわけ都市の魅力や土地利用の変化に関する課題を考察する。 東京、横浜、大阪、福岡の事例を通じて、この変遷のメカニズムと多様な都市形態を分析し、日本の都市沿岸部の未来を形作る「可能性のある領域」を明らかにする。
レミ・スコシマロは、地理学博士。トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学日本言語文化准教授。日本の都市中心部の社会人口学的再編、海面埋立地の開発、さらに広義では日本の土地開発、特に2011年3月11日の東日本大震災後の復興に関心を持つ。著者である Atlas du Japon, l'ère de la croissance fragile (Autrement, 2018) は日本語訳『地図で見る日本ハンドブック』(原書房、2018年)が出版されている。
【司会】ラファエル・ランギヨン(日仏会館・フランス国立日本研究所) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
Entre philologie et linguistique : éléments de méthodologie pour aborder les textes missionnaires en japonais romanisé
使用言語:フランス語 (通訳なし)
| 日時: | 2025年04月22日(火) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | salle 601& en ligne |
| 講演者: | Maxime BONNET (EPHE - CRCAO) |
Les inscriptions au séminaire seront ouvertes sur le nouveau site de l'IFRJ-MFJ qui sera mis en ligne le 14 avrilLa documentation chrétienne rédigée sur l'archipel antérieurement à la période de fermeture constitue un observatoire de premier ordre pour l'étude historique de la langue japonaise moyenne et moderne. Maxime Bonnet est philologue et linguiste. Diplômé de lettres classiques, de linguistique, de japonais et de FLE, il prépare pour sa thèse de doctorat, dirigée par le professeur Jean-Noël Robert, une nouvelle édition des Fables ésopiques rédigées en Amakusa (1593), assortie d'un commentaire et d'un appendice grammatical. Modérateurs : Sania CARBONE (Inalco, IFRAE), Raphaël LANGUILLON (IFRJ-MFJ), Étienne MARQ (CRCAO) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日仏会館フランス事務所 / イベント・カレンダー > 2025年4月