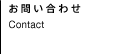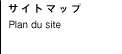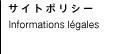2025年3月のイベント
- 日仏翻訳マスタークラス
- 日仏の女性たちと文学をめぐって
- オウム真理教の内外に蔓延した「マインド・コントロール幻想」
- Cancer pédiatrique de la thyroïde à Fukushima : politique du risque et engagement civil
| 日時: | 2025年03月01日(土) 14:00〜17:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
| 講演者: | コリーヌ・アトラン(作家・翻訳家) |
|
2003年小西財団日仏翻訳文学賞受賞者のコリーヌ・アトラン氏の指導による、日本語からフランス語への実践的な翻訳ワークショップ(全6回のうちの第3回目) アマチュア・プロを問わず、翻訳家を志す方、翻訳家として活躍している方、翻訳出版に関心がある方などを対象としたワークショップです。翻訳家の職業をより深く理解し、具体的な例に基づいた演習を行います。 コリーヌ・アトラン氏は自身の仕事についてフランス語および日本語で語り、その後日本語からフランス語への翻訳の演習を行います。 主題 : 村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』、林 芙美子『茶色の眼』
コリーヌ・アトラン
|
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年03月08日(土) 14:00~16:30 |
|---|---|
| 場所: | 1階ホール |
| 講演者: | 桐野夏生(作家)、マルティーヌ・リード(文学研究者、リール第三大学名誉教授) |
|
日仏女性研究学会は、国際女性デーを記念して、「女性と文学」をテーマに2日間にわたる連続イベントを開催します。 【講師プロフィール】
マルティーヌ・リード(文学研究者、リール第3大学名誉教授) ※このイベントは、国際女性デー記念連続イベント「女性と文学----過去・現在・未来」の一環として行われ、3月9日(日)開催のセミナー「フランスにおける文学史と女性----マルティーヌ・リード氏を迎えて」と連動しています。セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.fmfj.or.jp/events/20250309.html 【ディスカッサント】トマ・ガルサン(日仏会館・フランス国立日本研究所) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年03月20日(木) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | 601室&オンライン |
| 講演者: | 大田俊寛(埼玉大学) |
会場参加:定員に達したためお申込みを締め切りましたオンライン参加:こちら をクリックしZoomウェビナーにご登録ください1995年3月20日、地下鉄サリン事件という大規模テロを起こしたオウム真理教。その暴走を後押ししたのは、一体何だったのか。従来の日本社会では、「マインド・コントロール(あるいは洗脳)」の理論によってオウムを説明しようとする試みが盛んに行われてきた。すなわち、オウムの信者は教団によって完全にマインド・コントロールされており、自由意志を失っていた、というのである。 とはいえ、マインド・コントロールという概念は、決して科学的・学問的に確立されているわけではない。むしろ「疑似科学」と見なされることが多いほどである。果たして本当に、オウムの内部ではマインド・コントロールが実現していたのだろうか。 本講演では、マインド・コントロールという理論を、科学ではなく「幻想」と捉え、そうした幻想がオウムの内外にどのような仕方で存在してきたのか、ということを考察する。その際に一つの発端となったと思われるのは、1950~60年代にアメリカのCIAで行われたマインド・コントロール実験、「MKウルトラ計画」である。同計画は失敗に終わったものの、以降の新宗教運動・オカルティズム・陰謀論に大きな影響を与え、オウムでもまた、それをモデルとした人体実験が行われていた。さらには「反カルト」の側でも、新宗教運動に参加している人々はマインド・コントロールを受けていると見なされ、そこから離脱させるために「ディプログラミング」が必要である、と主張されたのである。 こうした観点から再考すると、実にオウム事件は、マインド・コントロール幻想に取り憑かれた二つの集団の衝突であった、とさえ映るようになる。そして日本社会は、マインド・コントロール理論を適切に批判しなかったために、オウム事件の本質を誤解したばかりか、宗教問題に冷静に対処する方法を見失ったように思われるのである。
大田俊寛は1974年生まれ。専門は宗教学・思想史。古代キリスト教の異端である「グノーシス主義」の研究により、東京大学で博士号を取得し、2009年に『グノーシス主義の思想――"父"というフィクション』を公刊。その後はオウム真理教の研究を手掛け、『オウム真理教の精神史――ロマン主義・全体主義・原理主義』(2011年)と『現代オカルトの根源――霊性進化論の光と闇』(2013年)を公刊。現在は埼玉大学においてリベラル・アーツ教育を担当しており、2023年に西洋宗教思想史の講義録『一神教全史』を公刊した。 【司会】アントナン・ベシュレール(日仏会館・フランス国立日本研究所)
シンポジウムの全てのプログラムをzoomより視聴可能です。ご登録はこちら |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
Cancer pédiatrique de la thyroïde à Fukushima : politique du risque et engagement civil
使用言語:フランス語 (通訳なし)
| 日時: | 2025年03月25日(火) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | salle 601 & en ligne |
| 講演者: | Chiara Ramponi (Univ. de Tôhoku) |
InscriptionAprès inscription, les participants en distanciel recevront un lien Zoom le jour de la séance. Cette étude explore la controverse médicale entourant les cas de cancer pédiatrique de la thyroïde émergés après la catastrophe de Fukushima et cherche à examiner à la fois les aspects épistémologiques du débat, dans le cadre de la science des rayonnements, et les activités de deux associations citoyennes créées pour soutenir les patients et leurs familles. La première partie offre un aperçu de l'évaluation épidémiologique de ces cancers et des examens cliniques menés depuis 2011 par l'Université Médicale de Fukushima. Tandis que les autorités sanitaires nationales et internationales (y compris l'UNSCEAR et l'OMS) attribuent le nombre élevé de diagnostics à l'utilisation de technologies avancées, en excluant la possibilité d'un lien avec l'accident nucléaire, les associations citoyennes et les experts qui collaborent avec elles dénoncent des estimations biaisées de l'exposition et des défauts méthodologiques. Mon analyse vise à mettre en évidence comment le dépistage et la communication scientifique autour de celui-ci reproduiraient des tendances discursives et des stratégies rhétoriques observées à Tchernobyl, visant à "invisibiliser" le lien entre risque sanitaire et radiation. La deuxième partie s'intéresse au rôle des associations, qui poursuivent trois objectifs : contester l'évaluation officielle, soutenir financièrement les patients et offrir un espace de soutien moral face à la stigmatisation sociale. La recherche cherche également à fournir un premier cadre pour l'analyse du procès civil intenté par 7 patients contre TEPCO, qui constitue une tribune pour remettre en question le récit officiel de la reconstruction et du désastre en tant qu'événement finalement surmonté.
Pendant son master en anthropologie, ethnographie et ethnolinguistique à l'Université Ca' Foscari (Venise), Chiara RAMPONI s'est intéressée à la science citoyenne avec un mémoire portant sur l'impact micro-social de la contamination radioactive des denrées alimentaires dans la ville de Tamura (Fukushima), après l'accident du 2011. Avec une bourse doctorale MEXT à l'Université du Tohoku (Graduate School of Environmental Studies) elle étudie à present la controverse médicale entourant les cas de cancer pédiatrique au niveau de la thyroïde, apparus dans la région de Fukushima dans le cadre du Fukushima Health Management Survey. En août 2023, elle a reçu une bourse de la Fondation Takagi Jinzaburo afin de réaliser les interviews auprès des associations des citoyens qui soutiennent les patients et les familles concernées. Elle participe au Mitatelab, un group de recherche franco-japonais qui étudie l'après-Fukushima d'un point de vue interdisciplinaire.
Modérateurs : Sania CARBONE (Inalco, IFRAE), Raphaël LANGUILLON (IFRJ-MFJ), Étienne MARQ (CRCAO) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日仏会館フランス事務所 / イベント・カレンダー > 2025年3月
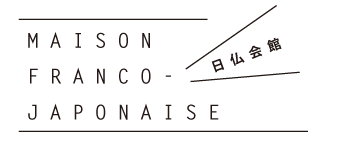
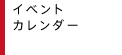
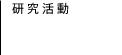
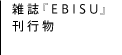
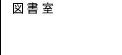
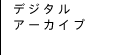
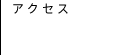
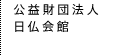
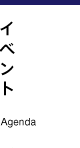


 ©Wakaba Noda (TRON)
©Wakaba Noda (TRON)