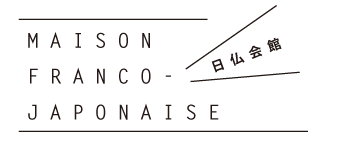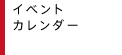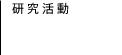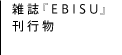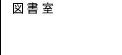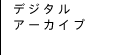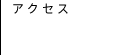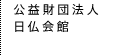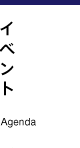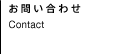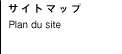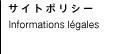2025年2月のイベント
- Housing and material reuse: toward a sustainable business model for wooden architecture in Japan
- 分断都市を超えてー2020年以降の縮退郊外における変化
- 日仏翻訳マスタークラス
- フランスのジャポニスムと印刷文化
- Les enjeux politiques juridiques et sociaux du nom des époux au Japon
Housing and material reuse: toward a sustainable business model for wooden architecture in Japan
使用言語:英語 (通訳なし)
| 日時: | 2025年02月03日(月) 12:30-14:00 (JST) |
|---|---|
| 場所: | room 601 & online |
| 講演者: | Masaya SUGITA (Kameoka Construction Co., Ltd.,) |
Online participation:
|
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年02月14日(金) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
| 講演者: | 久保倫子(筑波大学) |
|
大都市圏の外延的拡大と大都市圏内の機能分化に特徴づけられた20世紀の都市の構造は,21世紀に入り大きな転換期を迎えている。この中で,長期的に衰退傾向が継続する縮退都市化,大都市圏内での分断化,これに加えて日本では1970~80年代に開発された外部郊外での住民および建造環境の高齢化が顕著となっている。地方都市では,空き家や空き地の増加,中心市街地の衰退などが問題視されてきた。この背景には,グローバリゼーションにともなう都市間競争に打ち勝つために規制緩和と都心再開発を好む起業家的都市化が進んだことがある。その結果,継続的に都市への資本投下が続いた都心部と続かなかった郊外,特に大都市圏の外延的拡大が最大限となって生じた外部郊外とでは,居住環境上の明暗が生じている。しかしながら,2020年代にはいり,一部の郊外地区では,データセンターおよび流通拠点として新たな開発が進む地区や,隣接自治体で就業する若年核家族世帯による住宅取得先として評価されるようになり人口増加に転ずる住宅地区も確認されるようになってきた。後者の代表例が竜ケ崎ニュータウンである。本講義では,東京大都市圏の外部郊外にあたる龍ケ崎市における実証研究を中心に,郊外住宅地の将来像を検討する。
【講師】久保倫子(筑波大学) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年02月15日(土) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
| 講演者: | 吉川一義(京都大学名誉教授) |
|
定員に達したためお申込みを締め切りました。 2021年小西財団日仏文学翻訳特別賞受賞者の吉川一義氏の指導による、フランス語から日本語への実践的な翻訳ワークショップ(全6回のうちの第2回目) アマチュア・プロを問わず、翻訳家を志す方、翻訳家として活躍している方、翻訳出版に関心がある方などを対象としたワークショップです。翻訳家の職業をより深く理解し、具体的な例に基づいた演習を行います。 吉川一義氏は自身の仕事について日本語で語り、その後フランス語から日本語への翻訳の演習を行います。 主題 : プルースト『失われた時を求めて』
吉川一義 お申込み お申込み方法 定員に達したためお申込みを締め切りました。 【主催】日仏会館・フランス国立日本研究所
|
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2025年02月21日(金) 10:00〜18:00 |
|---|---|
| 場所: | 1階ホール |
|
本と挿絵入り雑誌の歴史は、1870年代から戦間期の間におけるジャポニスムの隆盛と発展に密接に関係している。芸術的かつ学術的なジャポニスムの媒体でありベクトルでありながら、ジャポニスムの印刷物は決して単一の表現の対象となることはなかった。サミュエル・ビングの旗艦誌 『Le Japon artistique』(1888-1891年)や、マラルメやクローデルの著作、ウジェーヌ・グラッセ、、ジャン=ジョルジュ・オリオールといった印刷業者、版画家、偉大な装飾芸術家やタイポグラファーが美術雑誌や装飾雑誌のレイアウトやイラストレーション、または学術作品に果たした役割についての研究に私たちは事欠くことはない。本シンポジウムは、文字通りの意味での「日本の印象」を消耗させることを目指すのではなく、絵画、彫刻、建築と並んで、フランスにおけるジャポニスムの普及を絶えず支えてきた紙のモニュメントへのオマージュを集めることを目的としている。、エミール・ヴェルハーレン、ピエール・ロティ、ガブリエル・ムーリーなどの出版物がその役割を物語っている。 フレーミングとタイポグラフィの配置を導く絵画的なジャポニズムとの絶え間ない相互作用の中で、「documents d'art et d'industrie」特有の革新的な美を生み出し、日本の本を特徴づける要因となった。これらのケーススタディの主たる狙いは、ジャポニスムの普及者としての印刷物にスポットを当てることである。
【登壇者】ソフィー・バッシュ (ソルボンヌ大学、フランス大学研究院、CELLF フランス語フランス文学研究センター、CNRS/パリ・ソルボンヌ大学 UMR 8599)、ギィ・デュクレイ(ストラスブール大学) 、エリザベート・エメリー(モントクレア米国ニュージャージーニュー州立大学)、ジャン=ルイ・アケット(ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学)、林 洋子(兵庫県立美術館館長)、ファブリス・コードン(ソルボンヌ大学)、セゴレーヌ・ルメン(パリ・ナンテール大学名誉教授) 、クリストフ・マルケ(フランス国立極東学院)、ギヨーム・メタイエ(フランス国立科学研究センター 、CELLF フランス語フランス文学研究センター、CNRS/パリ・ソルボンヌ大学 UMR 8599)、三浦 篤(東京大学名誉教授、大原美術館館長)、及川 茂(日本女子大学名誉教授)、岡部 昌幸(帝京大学名誉教授、荏原畠山美術館館長)、マリアンヌ・シモン=及川(パリ・シテ大学)、寺田 寅彦(東京大学)、エレーヌ・ヴェドリーヌ(ソルボンヌ大学、ELLF フランス語フランス文学研究センター、CNRS/パリ・ソルボンヌ大学 UMR 8599)、ベルナール・ヴイユ(ソルボンヌ大学名誉教授、CELLF フランス語フランス文学研究センター、CNRS/パリ・ソルボンヌ大学 UMR 8599)、ミシェル・ワッセルマン(立命館大学名誉教授)
関連データ:» Programme.pdf |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
Les enjeux politiques juridiques et sociaux du nom des époux au Japon
使用言語:フランス語 (通訳なし)
| 日時: | 2025年02月25日(火) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | salle 601 & en ligne |
| 講演者: | Gérard LEGRIS (Inalco-IFRAE) |
InscriptionAprès inscription, les participants en distanciel recevront un lien Zoom le jour de la séance. Ma recherche a pour objet d’analyser si et comment une cause sociale, portée par un mouvement citoyen peut parvenir à faire évoluer la loi dans un domaine touchant aux droits individuels des citoyens et à l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle prend comme terrain d’observation la revendication concernant la réforme du dispositif régissant le nom des époux et son interaction avec le système d’État civil japonais, le Koseki. Ce combat vise à réformer système de l’unicité du nom de famille qui oblige l’un des époux à devoir abandonner son nom de naissance pour obtenir la validation légale du mariage, et obtenir une alternative permettant aux individus de conserver leur nom de naissance tout au long de leur vie. Après avoir présenté ce dispositif et ses racines historiques, je me propose de soumettre à la discussion les différentes dimensions qui nourrissent les tensions qui en découlent entre les intérêts individuels des citoyens, de l’État et de la société : la dimension judiciaire, du fait de la judiciarisation de leur cause par les militants, La mise en œuvre d’une stratégie de lobbying visant l’arène politique et institutionnelle ainsi que l’activation des canaux extérieurs (gaiatsu, 外圧), notamment via les organisations internationales. Enfin je présenterai pour discussion les différentes activités de terrain que j’envisage de conduire lors de mes prochains séjours au Japon afin de mieux comprendre et analyser les attitudes des militants, des différentes catégories d’acteurs engagés dans ce combat aussi bien que celles de ses opposants et recueillir les éventuels conseils et avis susceptibles de m’être adressés pour la poursuite de mes travaux.
Titulaire d’un Master en langue, littérature et civilisation japonaise en 2021 avec un mémoire intitulé « les enjeux politiques et sociaux du nom des époux au Japon et le lobbying citoyen : un cas d’école » Gérard LEGRIS, prépare actuellement, sous la direction d’Isabelle Konuma, une thèse ( INALCO – IFRAE) qui poursuit et approfondit cette question. Il a ainsi repris des travaux universitaires après une carrière de plus de 30 années au service des institutions européennes qui l’a amené notamment à occuper des fonctions diplomatiques (Conseiller) à Tokyo entre 1991 et 1996 en tant que Porte-parole, chef du service de presse et d’information de la délégation de l’UE au Japon. Gérard LEGRIS est un ancien auditeur de l’IHEDN. Modérateurs : Sania CARBONE (Inalco, IFRAE), Raphaël LANGUILLON (IFRJ-MFJ), Étienne MARQ (CRCAO)
|
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日仏会館フランス事務所 / イベント・カレンダー > 2025年2月