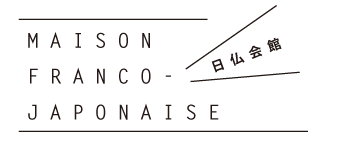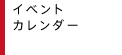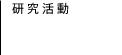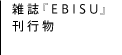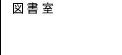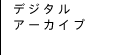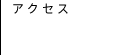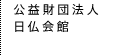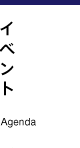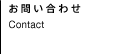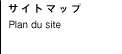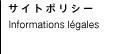2024年6月のイベント
- 大都市とメガイベント - オリンピック・パラリンピックと万国博覧会の一世紀半にわたる日仏の都市計画 -
- 大都市とメガイベント - オリンピック・パラリンピックと万国博覧会の一世紀半にわたる日仏の都市計画 -
- 日本の写真遺産と芸術遺産の研究のための新デジタルツール
- Le Japon, un pays d’immigration ? Une analyse terminologique de la politique migratoire japonaise de 1990 à nos jours
| 日時: | 2024年06月03日(月) 9:30〜17:00 |
|---|---|
| 場所: | 1階ホール |
|
2024年6月3日(月)・4日(火) 日本は歴史上、3度の夏季オリンピック(東京:1940年、1964年、2020年)と3度の冬季オリンピック(札幌:1940年、1972年、長野:1998年)を開催してきた。また、多数の万国博覧会がこの国で開かれ、次回は2025年の大阪万博が待機している。フランスもまた同様だ。パリはこれまでに3度のオリンピックを開催しただけでなく、2024年夏季オリンピックの開催都市でもある。2020年代のメガイベントの日仏間の往来 - Tokyo2020、Paris2024、Osaka2025-は、歴史的な日仏間の対話の契機をなし、イベントを通じた2国間の都市開発モデルの循環や競争を観察できるまたとない機会である。 この日仏国際シンポジウムでは、フランスと日本における、イベントによる都市建設のダイナミクスを、都市開発の批判的政治経済学の観点から分析することを試みる。
【講師】荒又美陽(明治大学)、大城直樹(明治大学)、成瀬厚(独立研究者)、杉山和明(流通経済大学)、ニコラ・フェラン(ソリデオ社)、タニア・ブラガ(国際オリンピック委員会)、ミシェル・コーベル(ストラスブール大学)、小笠原博毅(神戸大学)、アンドレア・百合・フロレス・漆間(福井県立大学)、樽野吉宏(大阪都市計画局)、稲田義久(甲南大学名誉教授)、マニュエル・タルディッツ(建築家、みかんぐみ)、港 千尋(多摩美術大学)、マルティーヌ・ドロズ(CNRS)、ファブリス・アルゴネス(ルーアン大学)、ラファエル・ランギヨン(日仏会館・フランス国立日本研究所) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1日目 - 2024年6月3日 :オリンピックとパラリンピック、スタジアムから街へ 9:00-9:30 一般受付 9:30-10:00 - 開会の辞 10:00-11:00 - 基調講演 メガイベントとグローバルシティの現在 --東京とパリの都市(再)開発から考える-- 荒又 美陽(明治大学) 11:00-12:30 - 第1 部 イベントを超えた開催都市の整備 2つの東京オリンピックと都市再開発 --資本主義的風景の前面化について-- 大城 直樹(明治大学) 12:30-14:00:昼休憩 14:00-15:30 - 第2 部 オリンピックとパラリンピックのインフラの長期にわたる構築と(再)利用 パリ2024オリンピック・パラリンピックに向けたインフラ整備 ニコラ・フェラン(ソリデオ社マネージングディレクター) 15:30-17:00 - 第3 部 反オリンピック・パラリンピック運動 ヨーロッパにおける2024年オリンピック招致立候補への市民参加:民主主義の刷新か、それとも単なる戦略的手段か? ミシェル・コーベル(ストラスブール大学) * ビデオメッセージ
シンポジウム2日目へのお申し込みはこちらから 【重要】公益財団法人日仏会館への電話のお掛け間違いにご注意ください。 お問い合わせメールアドレス:contact@mfj.gr.jp |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2024年06月04日(火) 14:00〜19:00 |
|---|---|
| 場所: | 1階ホール |
|
2024年6月3日(月)・4日(火) 日本は歴史上、3度の夏季オリンピック(東京:1940年、1964年、2020年)と3度の冬季オリンピック(札幌:1940年、1972年、長野:1998年)の開催権を取得した。また、多数の万国博覧会がこの国で開かれ、次回は2025年の大阪万博が待機している。フランスもまた同様だ。パリはこれまでに2度のオリンピックを開催しただけでなく、2024年夏季オリンピックの開催都市でもある。2020年代のメガイベントの日仏間の往来 - Tokyo2020、Paris2024、Osaka2025-は、歴史的な日仏間の対話の契機となり、イベントを通じた2国間の都市開発モデルの循環や競争を観察できるまたとない機会である。 この日仏国際シンポジウムでは、フランスと日本における、イベントによる都市建設のダイナミクスを、都市開発の批判的政治経済学の観点から分析することを試みる。
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2日目 - 2024年6月4日 :万国博覧会と(未来の)都市環境づくり 13:30-14:00:一般受付 14:00-14:15:開会の辞 14:15-15:45 - 第4 部 1970年から2025年まで万国博覧会を通じた大阪・関西の発展 1970年の大阪万博開催をめぐる地方競争 アンドレア百合・フロレス漆間(福井県立大学) 15:45-17:15 - 第5 部 パビリオン、現実と未来のビジョンの間にある具体的なユートピア パビリオンのパラドックス マニュエル・タルディッツ(建築家、みかんぐみ) 17:15-17:45:休憩 17:45-18:45 - 基調講演 マッピングエキスポ--地図で見る万国博覧会-- ファブリス・アルゴネス(ルーアン大学) 18:45-19:00 - 閉会の辞 シンポジウム1日目へのお申し込みはこちらから 【重要】公益財団法人日仏会館への電話のお掛け間違いにご注意ください。 お問い合わせメールアドレス:contact@mfj.gr.jp |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2024年06月14日(金) 16:00~20:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
|
定員に達したためお申込みを締め切りました 20 年以上前から、視覚文化からの膨大な量のデータが、デジタル・ヒューマニティーズ(人文情報学)の推進のもとで蓄積されてきた。 今日では、人工知能(AI)のアプリケーションが猛烈なペースで開発されている一方で、コンピューターモデルのトレーニングにこれらのコーパスを動員して遺産画像の自動分析を可能にする、という問題が生じている。このように、ここ数年、美術史や写真史における人工知能の可能性を探る研究プロジェクトが進められている。これらのプロジェクトのほとんどはこれまで単独で進められてきたが、現在では、コーパス、経験、方法論、発展した倫理の共有を促進する取り組みが行われている。2023年10月、フランス国立ギメ東洋美術館(パリ)は、TEKLIA社と提携し、日本の古い写真コレクションの自動索引付けを可能にするモデルの開発を目的とした3年間のプロジェクトを開始した。(HikarIAプロジェクト、2023~2026年)このような背景をもとに、ギメ東洋美術館は、日本の写真・芸術遺産の研究に新技術、特に人工知能を活用することの課題について、日仏の専門家が長期的な対話を行うことを目的とし、このセミナーを開催する。
フェリス・ベアト「箱根, 芦ノ湖と箱根の村」 1866年頃 色付きの鶏卵紙に印刷 22,4 x 27,9 cm AP11400、フランス国立ギメ東洋美術館蔵 登壇者 : 高橋 則英 - 日本大学芸術学部 1978年、日本大学芸術学部写真学科卒業。1980年、日本大学芸術研究所修了。1989-90年、文化庁派遣在外研修員として米国ジョージ・イーストマン・ハウス国際写真博物館等で研修。2002年から日本大学芸術学部教授。現在、日本大学上席研究員、日本写真芸術学会会長。専門は写真史、画像保存。共著として『写真の保存・展示・修復』(日本写真学会画像保存研究会編、武蔵野クリエイト、1996年)、『シリーズ本を残す10 写真資料の保存』(日本図書館協会、2003年)、編著として『レンズが撮らえた 日本人カメラマンの見た幕末明治』(山川出版社、2015年)、『文化財としてのガラス乾板-写真が紡ぎなおす歴史像』(勉誠出版、2017年)、監修として『写真技法と保存の知識』(青幻舎、2017年)、『日本初期写真史 関東編』(東京都写真美術館、2020年)、『写真発祥地の原風景 幕末明治のはこだて』(東京都写真美術館、2022年)など。 柳生紀子 - 長崎大学附属図書館 長崎大学附属図書館学術情報管理班班長。図書館業務の傍ら、2002年よりシステム管理者として古写真データベースの運用に携わる。長崎大学が所蔵する古写真のデータベースである「幕末・明治期日本古写真データベース」、および他機関の古写真との統合検索を可能とした「日本古写真グローバルデータベース」の構築スタッフの一人。 谷 昭佳 - 東京大学史料編纂所 東京大学史料編纂所 史料保存技術室 写真担当 技術専門員。東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター「古写真研究プロジェクト」にて、2002年以来国内外に点在する19世紀日本関係古写真の調査研究に従事している。2020年には日本写真協会賞学芸賞を受賞。現在進行中の「幕末明治期古写真の調査とその解析・復元・保全を総合的に捉える写真史料学の構築」(JSPS科研費23H00654)では研究代表者を務める。 赤間 亮 - 立命館大学アート・リサーチセンター 北米や欧州の博物館・図書館が所蔵する日本文化資源のデジタル化プロジェクトを進めている。運営する浮世絵や古典籍データベースは世界最大である。大規模な文化資源情報を背後に、デジタルツールを加えたオンライン研究空間を構築し、文化芸術系を中心とする研究者に提供している。浮世絵の類似画像検索に加え、人物(とくに役者)の古写真や絵葉書に対して、顔認識による検索システムの開発を開始する予定である。 スッパキット・パイサーン・ウォラポン - 東京大学大学院情報理工学系研究科 東京大学大学院情報理工学系研究科特任准教授。2012年9月に同研究科の博士課程を修了後、2013年から2015年まで国立情報学研究所(NII)特任研究員を経て、2015年東京大学助教授、2016年からは特任講師を務め、その後現職。主要な研究分野は組み合わせ最適化とそのプライバシー・セキュリティ。これまでに60本以上の研究論文が採択され、20人以上の大学院生の指導を行っている。 北本 朝展 - 国立情報学研究所 東京大学工学系研究科電子工学専攻修了。博士(工学)。現在、情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 人文学オープンデータ共同利用センター センター長、国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 教授、総合研究大学院大学 複合科学研究科 情報学専攻 教授。データ駆動型サイエンスのアプローチを人文学や地球科学、防災などの分野で幅広く展開している。そして、オープンな学術研究の基盤となるデータベースやソフトウェアを公開し、研究者や市民の利用は毎年数百万人に達している。またオープンサイエンスの展開に向けた超学際的研究コラボレーションにも取り組む。文化庁メディア芸術祭 アート部門 審査委員会推薦作品、情報処理学会 山下記念研究賞、じんもんこんシンポジウム 最優秀論文賞、デジタルアーカイブ学会 学術賞(研究論文)、グッドデザイン賞などを受賞。 デサントゥール・エドワール - フランス国立ギメ美術館 デサントゥール・エドワールは、パリの国立ギメ東洋美術館の写真コレクションの学芸員。同美術館は、1853年以降のアジアで撮影された60万点に及ぶ様々なタイポロジーの写真を所蔵する。美術史家としての顔も持ち、東南アジアの写真の起源を専門とする。現在、19世紀、インドシナにおけるフランスの植民地事業の中の写真の位置づけをテーマとした博士論文を執筆中。セント・アンドリュース大学/ル・アーヴル・ノルマンディー大学) ケルモーバン・クリストファー - TEKLIA ケルモーバン・クリストファーは、エンジニア、情報工学博士。スイス連邦工科大学ローザンヌ校、モントリオール大学の研究員、A2iA研究チーム代表を務める。自動文書処理を専門とする会社・TEKLAを設立。手書き認識とドキュメント分析に適用される機械学習とディープラーニングにフォーカスした事業を行う。人文情報学の分野における数多くの共同研究プロジェクトに参加。 【講師】高橋 則英(日本大学)、柳生 紀子(長崎大学)、谷 昭佳(東京大学)、赤間 亮(立命館大学)、スッパキット・パイサーン・ウォラポン(東京大学)、北本 朝展(国立情報学研究所)、エドワール・デサントゥール(フランス国立ギメ東洋美術館)、クリストファー・ケルモーバン(TEKLIA) *このワークショップは、フランス語、日本語(同時通訳付き)、一部英語(通訳なし)で行われます。
【重要】公益財団法人日仏会館への電話のお掛け間違いにご注意ください。 お問い合わせメールアドレス:contact@mfj.gr.jp
関連データ:» Programme FR_JP.docx |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
Le Japon, un pays d’immigration ? Une analyse terminologique de la politique migratoire japonaise de 1990 à nos jours
使用言語:フランス語 (通訳なし)
| 日時: | 2024年06月18日(火) 18 h - 20 h |
|---|---|
| 場所: | salle 601 & en ligne |
| 講演者: | Oumrati MOHAMED (Inalco, IFRAE) |
|
* Après inscription, les participants en distanciel recevront un lien Zoom le jour de la séance. La révision de la Loi sur le contrôle de l'immigration en 2018 a introduit le visa de travail « Compétences spécifiques » (Tokutei ginō), marquant ainsi un tournant dans la politique d'accueil des travailleurs étrangers. Pour la première fois, cette nouvelle politique permet l'accueil officiel de travailleurs dans divers domaines tels que la construction, les soins infirmiers et le nettoyage de bâtiments. Auparavant, la politique d'accueil des travailleurs étrangers se limitait aux individus hautement qualifiés, et les travailleurs manuels ou moins qualifiés n'étaient pas officiellement admis à travailler au Japon, ou du moins aucun visa n'existait pour cette catégorie. Ce changement majeur s'est accompagné de réactions vives lors des débats parlementaires pour la création de ce visa. À l'époque, le Premier ministre avait dû expliquer que ce visa ne constituait pas une « politique d'immigration » (imin seisaku) et que les travailleurs étrangers recrutés étaient considérés comme des « talents étrangers » (gaikoku jinzai). Après l'obtention d'un Master en études japonaises en 2018 à l'université Paris Cité et un séjour à la faculté de droit de l'université Hitotsubashi en tant que lauréate de la bourse du MEXT (2019 - 2021), Oumrati MOHAMED s'est inscrite en doctorat à l'Inalco et y prépare une thèse intitulée : Devenir un pays d'immigration ? Résistances administratives et ouvertures législatives au Japon de 1990 à nos jours sous la direction d'Isabelle Konuma (Inalco - IFRAE) et Hélène Le Bail (Sciences Po - CERI). Modératrice : Sania CARBONE (Inalco, IFRAE) Renseignements : doctorantsmfj@gmail.com ou contact@mfj.gr.jp |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日仏会館フランス事務所 / イベント・カレンダー > 2024年6月