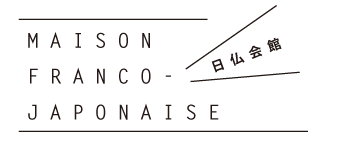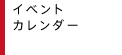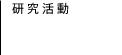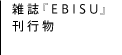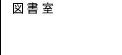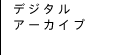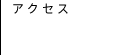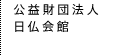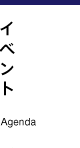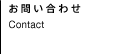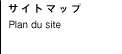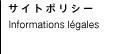2019年12月のイベント
- 博士課程の学生のためのセミナー
- 日本における貧困問題の認識とその変遷
- 共同性と同一性の狭間で揺れ動く「我々」:九鬼周造と1920〜1930年代
- 日仏会館図書室 読書会
8. バンド・デシネをフランス語で読む - 「日仏の翻訳者を囲んで」第16回
| 日時: | 2019年12月10日(火) 18:00〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | 601会議室 |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2019年12月16日(月) 18:30〜20:30 |
|---|---|
| 場所: | 601号室 |
| 講演者: | メラニー・ウルス(トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学) |
|
日本では貧困問題は長きにわたりタブーとされ、不可視化されてきたが、2000年代後半から社会問題としてメディアに取り上げられるようになった。数十年前から日常においてはほとんど耳にすることがなくなっていた「貧困」というワードが、2009年には日本中を席巻した。今日、貧困の存在は否定のしようもない現実である一方、社会的に問題として認識されているのは、ある一部の種類の貧困のみである。この講演では、戦後から今日までの貧困問題をめぐる認識の変遷を検証し、貧困が今日ふたたび社会問題として可視化され、容認されるようになった要因を探る。 プロフィール:
【司会】ソフィー・ビュニク(日仏会館・フランス国立日本研究所) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2019年12月18日(水) 18:30〜20:30 |
|---|---|
| 場所: | 1階ホール |
| 講演者: | シモン・エベルソルト (フランス国立極東学院) |
|
個人と普遍の直接的結合を説く大正期の普遍主義的個人主義に対して、九鬼周造は「具体」を把握しようとした。九鬼の作品においては、諸々の「具体」概念を特定できるが、それらは総合的に「我々」と呼ぶことができ、共同性と同一性の狭間で揺れ動いてる。本発表では、九鬼の著作を単に内在的に解釈するだけでなく、それを歴史的背景に関連づけ、「我々」とは何か、そもそも「我々」とは誰か、という問題を考えながら、1920〜30年代の日本思想史をも検討したいと思う。 プロフィール フランス国立極東学院 博士研究員、日本哲学研究チーム(IFRAE)共同責任者。専門は日本の哲学と思想史。2017年発表の博士論文「偶然と共同―日本の哲学者、九鬼周造」によりPSL研究大学による博士論文賞特別賞(人文)、パリ大学連盟(Chancellerie des Universités de Paris)主催によるリシュリュー賞、フランス日本研究学会主催による岡松慶久賞、渋沢・クローデル賞を受賞。同論文の刊行はVrin社より予定されている。 詳細はこちらのサイトから : 【司会】ベルナール・トマン(日仏会館・フランス国立日本研究所) |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2019年12月19日(木) |
|---|---|
| 場所: | 日仏会館図書室 |
|
バンド・デシネをフランス語の原書で読む読書会を当図書室で開きます。 BDの翻訳者である原正人氏が進行役をつとめ、一緒に読む読書会です。フランス語がある程度読めることが必要ですが、BDをはじめて読む方も、学生の方もぜひご参加ください。 Frederik Peeters, Lupus, T1, Atrabile, 2003.
作者のフレデリック・ペータースはスイスのバンド・デシネ作家。『青い薬』(原正人訳、青土社、2013年)と『KOMA―魂睡』(ピエール・ワゼム作、鈴木賢三訳、パイインターナショナル、2014年)が邦訳されています。 今回取り上げるLupusは、2003年に第1巻が出版され、2006年に全4巻で完結した作品。主人公のリュピュスは学業を終えたところ。今後の予定がはっきりしているわけでもなく、現在は宇宙を旅行中。軍隊を退役したばかりの幼馴染のトニーと一緒にさまざまな惑星をめぐっては、行く先々で釣りを楽しんでいる。ふたりの次の目的地は惑星ノラド。入国審査を済ませ、雨宿りをするために入ったバーでサナという女性と出会う。それは彼らの運命をすっかり変えてしまう出会いだった……。 ※2011年に出版された4巻を全1巻にまとめた合本版の表紙です。 今回も同日の昼と夜2回に分けて開催します。2回とも使用するテキストは同じですので、参加希望の方はどちらかの回にご参加ください。開催日時①:2019年12月19日(木)15時~16時半 開催場所:日仏会館図書室 参考図書室(3F) 開催日時②:2019年12月19日(木)18時半~20時 開催場所:日仏会館図書室(3F) 定員:各15名 参加:無料 参加方法:参加希望時間、お名前、ご連絡先、ご所属を明記してメールでお申込みください。読書会で使用するテキストについては図書室でご用意いたします。詳細はお申込みの際お知らせいたします。尚、出版社より当読書会でテキストを使用する許諾を得ております。 連絡先:日仏会館図書室 |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
| 日時: | 2019年12月26日(木) 18:30〜20:00 |
|---|---|
| 場所: | 日仏会館図書室 |
|
三澤慶展氏を囲んで 聞き手:野澤 丈二 氏(帝京大学、日仏会館・フランス国立日本研究所 協力研究員) 日仏会館図書室では、フランス語と日本語の翻訳に携わる方々をお迎えし、翻訳についてお話しを伺う会を開いています。 第16回となる今回は、パリ通訳翻訳高等学院(ESIT)をご卒業後、実務翻訳家としてご活躍されています三澤慶展氏をお迎えいたします。 【プロフィール】 英仏日の実務翻訳家。上智大学文学部英文科卒業後、パリ通訳翻訳高等学院(ESIT)で翻訳科修士号を取得。2016年よりフリーランス翻訳者として活動。法律、経済、ラグジュアリーを中心とした実務翻訳を手掛け、独立行政法人や国際機関の翻訳も行っている。 日時 2019年12月26日(水)18:30~20:00 場所 日仏会館図書室 使用言語:日本語 定員 20名 お申込み方法:下記のメールアドレスに、お名前、ご所属、ご連絡先を明記して、件名を「日仏の翻訳者を囲んで」としてお申込みください。図書室業務は18時で終了いたしますが、開催時間まで図書室をご利用いただけます。 連絡先:日仏会館図書室 〒150-0013 渋谷区恵比寿3-9-25 日仏会館3F Tel : 03-5421-7643 Fax : 03-5421-7653 Mail : biblio@mfj.gr.jp 開室時間:火~土 13h~18h |
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日仏会館フランス事務所 / イベント・カレンダー > 2019年12月