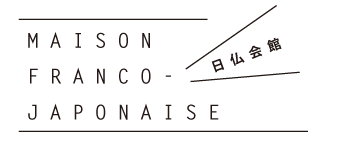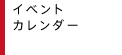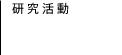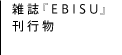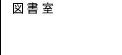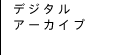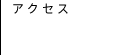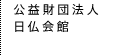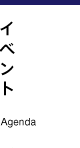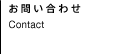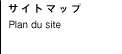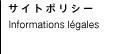2017年1月のイベント
連続講演会《日本研究の現在》
使用言語:
フランス語 (通訳付き)
日時:
2017年01月17日(火) 18:30〜20:30
場所:
1階ホール
講演者:
ピエール・スイリ(ジュネーヴ大学)
VIDEO Moderne sans être occidental (Gallimard, 2016)、Aux origines du Japon d'aujourd'hui (Gallimard, 2016)がある。
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日時:
2017年01月18日(水) 18:00〜20:00
場所:
601号室
講演者:
ピエール・スイリ(ジュネーヴ大学)
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日時:
2017年01月23日(月) 18:00〜20:00
場所:
1階ホール
講演者:
安藤裕康(国際交流基金理事長)
http://www.mfjtokyo.or.jp/mfjtokyo2/ja/events/details/738.html
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
『「夜想記念日」思想の夕べー海ー 世界と私たちをつなぐもの』(アンスティチュ・フランセ)前夜オープニング講演会
使用言語:
フランス語 (通訳付き)
日時:
2017年01月25日(水) 18:30〜20:30
場所:
1階ホール
講演者:
ベルナール・カラオラ(ピカルディ・ジュール・ヴェルヌ大学)
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
第33回渋沢・クローデル賞受賞記念講演
使用言語:
フランス語 (通訳付き)
日時:
2017年01月27日(金) 18:30〜20:30
場所:
1階ホール
講演者:
マルタン・ノゲラ=ラモス(フランス国立極東学院)
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日時:
2017年01月28日(土) 18:30〜20:30
場所:
1階ホール
講演者:
ドミニク・シャトー(パリ第1大学)
* イベントは、特に記載のない限り、すべて無料となっております。参加をご希望の方はお申し込みをお願いいたします。
日仏会館フランス事務所 / イベント・カレンダー > 2017年1月