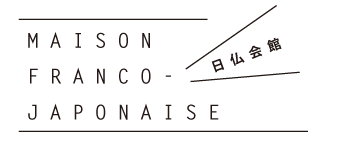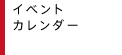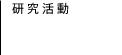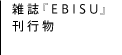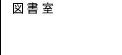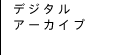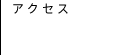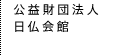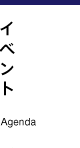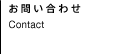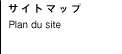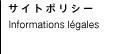【要旨】
今日家族を「つくる」ということは何を意味するのだろうか。個人もしくはカップルの選択に基づく行為と言えるであろうか。生殖補助医療技術を利用する場合、これらの問いは直接的な重要性を持つ。生殖補助医療の提供する枠組みに適合しない個人・カップルの意志は、その実現自体が難しいとされている。それでは生殖補助医療において、親としての適格性はどのように判断されてきたのだろうか。法規制が存在しない今日、この問いに対する答えは医療および司法の場にあると言えよう。その中でも特に親子関係と法律婚に焦点をあて、フランスとの比較を交えつつ考えていきたい。
【プロフィール】
小沼イザベルは現在、フランス国立東洋言語文化大学(INALCO)准教授であり、同大の日本文化研究所(CEJ)の研究員を務める。家族法および近現代の日本における生殖に関する政策を専門とする。主な業績は以下の通り。
« Le statut juridique de l’épouse au Japon : La question de l’égalité » (Recherches familiales, n° 7, 2010, p. 127-135) ; « Le statut juridique de la femme à travers le mariage pendant l’ère Meiji : entre inégalité, protection et reconnaissance » (in Emmanuel Lozerand et Christian Galan [ed], La Famille japonaise moderne [1868-1926]. Discours et débats, Philippe Picquier, Arles, 2011) ; « La chasteté, d’un devoir vers un droit : au prisme du débat (1914-1916) autour de Seitō » (Ebisu, n° 48, 2012, p. 147-166) ; « L’eugénisme et le droit – la politique de la reproduction au Japon » (in Béatrice Jaluzot [dir], Droit japonais, droit français, quel dialogue ?, SCHULTHESS, 2014, p. 95-109).
【司会】 ジャン=ミッシェル・ビュテル(日仏会館・日本研究センター)
【主催】 日仏会館フランス事務所
【助成】 日本を構成する人々研究会(フランス国立東洋言語文化大学・日
本研究センター)
【後援】 日仏女性研究学会
|